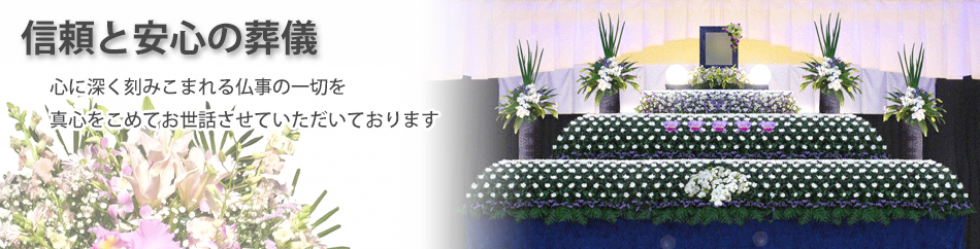葬送の変化 葬儀の歴史
変わる葬儀
わたしたちの生活のなかでも、多くの伝統的なしきたりを残しているものの一つが葬儀であると考えられています。
しかしこれまでも多少触れてきたように、わたしたちが「伝統的」と考えているものの起源が、実はそう古いものではないということはよくあることです。
庶民の葬儀について考えてみるならば、明治以降の近代化によって被った変化は、非常に大きなものがあるといえるでしょう。
特に都市部では、こうした変化が早い時期から受けいられており、現代においても葬儀の変貌は都市部、ことに東京のような大都会においてははなはだしいということができます。
東京以外の地方から超してこられ、自分が生まれ育った土地柄とは異なった葬儀の慣行に出会い、とまどわれた経験をおもちの人もいるかと思います。
それというのも、日本の各地には無数といってよいほどの葬儀の習慣やそれについての伝承が存在するからです。
しかし長らく東京に住み続けている人でも、よく思い出しみれば数十年前の葬儀と最近の葬儀はさまざまな点において異なってきていることに思い当たるでしょう。
それは、特に都市部での葬儀が現在まで大きく変貌してきているからです。
この節では、葬儀にかかわるいくつかの現象に焦点をあてながら、葬儀は変わらぬものであるという常識に挑戦してみることにしましょう。
日本は昔から火葬の国か
現在の日本の葬儀では、どんな宗教や宗派であっても、また、無宗教という人であっても、死者の遺体は火葬に付される場合がほとんどです。
1993年の統計では全国平均で97.9%の死者が火葬されています。
特に人口が密集し、墓地面積が不足している東京都では、ほぼ100%が火葬によって葬られています。
そんなところから、火葬は仏教と結びついた日本古来の伝統的な葬法であると考えられている面もあります。
たしかに欧米の主要先進国と火葬率は比較した資料でも、我が国の火葬率は断然高い値を示しています。
ヨーロッパ諸国のなかで高い火葬率を誇っているのは、チェコとイギリスで、1993年においてそれぞれ70%をわずかに超えているといったところです。
これに対して、フランスでは10%弱、スペインでは5%弱、イタリアにいたっては実に1.5%にすぎません。
カトリック教徒の多い国々では、まだまだ火葬率は低いようです。
ここには、死後の身体の復活を信仰する欧米のキリスト教習俗と、我が国との宗教的な風土の違いがと考えられてきました。
しかし、日本においても近代以前は必ずしも火葬が主流ではなかったことは、案外忘れ忘れ去られています。
日本における火葬の歴史は約1300年ほど前にさかのぼるといわれており、そこには仏教の影響があったというのがほぼ定説となっています。
しかし、当時火葬を受け入れていたのは、天皇家や貴族あるいは一部の僧侶たちだけであり、ほとんどの庶民は土俗的な葬儀形態を保っていたようです。
その後、仏教は民衆レベルにまで除々に浸透していきますが、それでも庶民の間では土葬のほうが一般的でした。
こうした状況を一変させたのが明治政府の政策でした。
それまでは、各地方、各地域の文化特色にしたがって行われていた死体の埋葬に、直接的、間接的に政府が介入していくようになります。
例えば明治政府は、明治の初年頃には火葬を突然禁止し、その2年後には解禁するという混乱した状況を呈しますが、これなどは庶民の風習に近代国家が直接に介入しようとして失敗した例です。
しかし、その後政府が埋葬地を限定し届け出制にした(現代の「墓地、埋葬等に関する法律」以下「埋葬法」という、につながる)ことや、人口の密集した都市部で、公衆衛生上の問題から土葬が禁止されたことなどから、都市部を中心に火葬場が次々と建設され、火葬率は除々に上昇していくもとになります。
そうはいっても1900年頃には火葬率は30%ほどにすぎませんでした。
その後、1950年には54%、1960年には63.1%,1970年には70.2%,1980年には91.1%と経済の高度成長と軸を一にするかのように急激に上昇し、1994年にはついに98.3%に達しました。
このようにみてきますと、日本において全国的に火葬が一般化したのは、やはり太平洋戦争後、特に生活の近代化が定着してからのことだということがわかります。
また世界の各国でも、近代化の進展とともに火葬率は除々に上昇しているようです。
宗教的な要因は無視しえないとしても、社会の近代化と火葬率の上昇は関連しあっていると考えられます。
その意味では、火葬という点に関しては、日本は世界でもっとも近代化の進んだ国であるということになります。
墓は先祖代々のもの
最近では、墓石の碑銘にさまざまな意匠を凝らしたものができてきましたが、以前は「○○家累代の墓」「△△家之墓」などと刻まれたものが多く見受けられました。
このように家族成員を単位にして合葬されているものを「家墓」といいます。
これに対して個人単位で埋葬されているのを「個人墓」と呼んでいます。
「先祖代々の墓」などと刻銘されてあると、こうした習慣が何百年も続いているかのように錯覚してしまいますが、実際のところどうなのでしょう。
家墓が建立されるようになるのは江戸時代末期以降のことであり、それが本格的に普及したのは明治末期であるとされています。
したがって家墓は、決して日本の伝統的な墳墓の形態ではないということが最近の研究では明らかになっています。
明治時代より前には「一人一墓」といい個人墓が主流だったのです。
例えば青山霊園には明治政府の土台を形づくった大久保利道の墓がありますが、墓碑銘は大久保氏個人のものとなっております。
家墓の普及にはいくつかの要因が考えられます。
明治以降、埋葬場所は許可制となり、行政からの制限を強く受けるようになったこと、火葬が普及していくことにより、一つの墓石の下に複数の遺骨を納めることが可能になってきたことなどがあげられます。
こうした外的な要因に加えて、庶民の意識面での変化を見逃すことはできません。
明治民法(1898年)では、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は家督相続の特権に属す」と規定されました。
それまで貴族や武士、あるいは豪農など社会の特権層にだけ許されていた家制度が一般大衆にまで法的に開放されたのです。
多くの人々がこれを積極的に受け入れたのではないでしょうか。
このような意識を背景として、家の墓を守り祖先の祭祀を絶やさないことが子孫、特に家長の本分であり、またそうしたことが日本古来の風習であると認識が高まり家墓が普及したと考えられます。
戦後は、こうした意味での家父長的な家制度は廃止されました。
現行の民法では「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する」とのみ記されており、家督相続権は否定されています。しかし、墓は家を単位にするという考え方は、いまも根強いものがあります。
霊柩車が誕生する前
現在の葬儀では、告別式が終了すると遺体は霊柩車にのせられて火葬場へと向かいます。
今こそ乗用車など珍しくもない時代となっていますが、自動車が普及する以前の葬儀では遺体はどのように運ばれていたのでしょうか。
霊柩車が日本に導入されたのは大正時代のなかば頃であり、東京、大阪、名古屋など比較的大きな都市で用いられはじめたようです。
大正年間といえば、路面電車や郊外電車は普及しはじめていましたが、自家用乗用車などは数えるほどしか走っていなかった時代です。
そんな時代に自動車で柩を運ぶというのは、大変モダンな発想だったのではないでしょうか。
そして近代的な利器の上に、柩を運ぶための輿を模した上屋をのせてしまったのが、現在でも多く見ることのできる宮型霊柩車なのです。
霊柩車が導入される前の葬儀では、自宅から埋葬地や火葬場まで、柩は駕篭や輿に乗せて運ばれました。
そして会葬者は葬列(野辺送りともいう)を組み、それに付き添いました。葬列を組むという慣習は、おそらく古代から形態を変えながらも長い時代にわたって行われてきたものと推測できます。
しかしながら葬列という慣習は、霊柩車の普及によって、大正から昭和にかけての短い期間に都市部を中心にして一挙に駆逐されてしまいます。
これはさまざまな原因が考えられますが、一つには葬列がもはや都市生活の実情にそぐわなくなったということがあります。
墓地や火葬場の遠隔化によって徒歩で墓地や火葬場に行くための時間がかかりすぎること、また葬列が路面電車や自動車などの運行を大いに妨げたことも考えられます。
その意味では、時代の要請にそぐわなければ長く続いた慣習でも変わっていくということを、葬列の消滅と霊柩車の普及が示しています。
最近では宮型霊柩車に代って、寝台車タイプの洋型霊柩車の普及もめざましいものがあります。
このあたりからも人びとの意識の移り変わりを読み取ることができます。
立派な祭壇は葬儀の必需品?
現在の葬儀において祭壇の段数の多さでその豪華さや盛大さを競うような風潮がみられます。
2段よりも3段が、それよりも4段の飾りのほうが格式の高い葬儀のように思われているかもしれません。
確かに祭壇は葬儀式場の中心にあり、司祭者も参列者も祭壇に向かって拝礼しますから、その部分が立派に見えることは葬儀全体の雰囲気にもかかわる重要な部分と考えられているのでしょう。
しかしながら祭壇の登場は東京が最も早くそれでも昭和初期であり、現在のような祭壇が葬儀で一般化するようになったのは昭和30年代からのことだといわれています。
それまでは、葬儀式場には柩と、枕机におかれた位牌や香炉などごく簡素な祭具が花環や供物などとともに並べられました。
それでも葬儀は立派に行われていたはずです。
人びとが葬儀の見ばえを気にするようになってきたのは、不特定多数の人びとが葬儀に集まるようになってからのようです。
人びとの社会関係が、ごく近くの地域住民だけに限られていた時代には、無駄な見栄をはらなくとも、逆に見栄をはったとしても、その家の内情は知れていますから、社会的地位や経済力の優劣はおのずと明らかでした。
しかし人びとが都市に集中することで住民の流動性が激しくなり、また居住地域をこえて社会関係が拡大していくと、社会的地位を誇示するために社会的体面に多くの人たちが気を使うようになってきます。
葬儀にかかわらず、結婚式などでの過剰なまでの外面志向の原因の一部はこのへんにありそうです。
しかし外面を取りつくろうことに追われて、葬儀自体が空虚になってきていることへの反省が生まれてきています。葬儀にかかわる人びとにとって本当に必要なものは一体何なのでしょうか。
核家族化する葬儀
生活様式が大きく変化しはじめてきた明治以降の葬儀の変化について、ごくかいつまんで説明してきましたが、このなかでも最も根本的な変化は、葬儀を現実に執り行う人びとは誰かという問題だと思います。
現在でも伝統的な生活習慣を残している地方では、すべての葬送儀礼を地域住民の助力によって行う場合があります。そこでは葬具の準備から、料理の支度、埋葬まですべての作業を近隣住民が中心になって取り仕切り、遺族はただ悲しみにくれていればよいということもあるようです。
このような形態の葬儀が万事都合よいかどうかはともかくとして、都市部を中心とした生活様式の近代化はもはやこの種の形態の葬儀を不可能にしてしまいました。かっては隣近所に住むということは、農作業などの労働をともにするということを意味していましたが、都市住民においては仕事と居住は一致していません。
したがって葬儀の際の援助を近隣に求めるのはむずかしくなってきました。
また葬儀の段取り、火葬や埋葬などの仕事も専門的な要素が強くなってきましたので、それぞれ独立したサービス業者に任せるほうが、何かと便利になってきました。
こうした変化のなかで、葬儀を実質的に取り仕切る中心は、地域共同体から家族に移り変わってきたのです。
しかも戦後の核家族化の流れのなかで、親族関係さえも薄らいできていますので、葬儀はいまや核家族を中心に行われているといっても過言ではないでしょう。
葬儀の主体の変化は、社会の最小単位の変化であるといってもよいかもしれません。
近代化という大きなうねりのなかで、葬儀の主体は、地域共同体からイエへ、イエから核家族へと移り変わってきました。
高度経済成長のある時期には企業葬ということが流行した時期もありますが、それも多くの人が職場を重要な社会の単位と考えていたからなのでしょう。
しかしいまのところ、社会の最小単位はだんだん小さくなっていくようです。今後は少子化や高齢化がさらに進展していますから、核家族の存在さえあやうくなるかもしれません。
そのときに葬儀の主体は、ついには個人にまで行き着いてしまうのか、あるいは必ずしも家族にはこだわらない新しい社会関係を見つけ出していくのか、現在はさまざまな可能性が試されている時代だということができます。