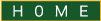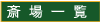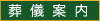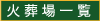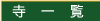|
いい葬儀・いいお葬式の案内
|
|||
|
2. 葬儀とはなにか
|
||||||||||||||||
| 社会は「わたし」の一部分 | ||||||||||||||||
| われわれは社会のなかで生まれ育ち、現に社会のなかで生活しているのですから、外部からの影響をまったく受けない独立した故人(=弧人)などというものが存在するはずもありません。 現にわたしたちは、今、日本語を用いて葬儀について考えているわけですが、これなども社会的に共有されている日本語という文化が、わたしたちの内部に自然な形で存在しているからこそ可能となるできごとなのです。 またわたしたちは、何か行動をおこそうとすれば、必然的に他人のっことも斟酌せざるをえません。わたしのある発言がまわりの人々にどのような影響をおよぼすのか、私が失業すると家族の生活にどのような困難が待ち受けているか、他者とかかわる多数のことがらをわたしたちは常に考慮に入れながら行動しています。このように「わたし」の内部には、すでに他者や社会が組み込まれているのです。そして多くの人に共通する「社会」を内部にわかちもった「わたしたち」が寄り集まって社会をつくっているのです。つまり社会は「わたし」を構成する一部分なのであり、同時にまた「わたし」は社会を構成する一部分でもあるわけです。 |
||||||||||||||||
| わたしのなかの小さな死 | ||||||||||||||||
| このように考えてきますと、「わたし」の内部に深く根をおろしている他者の死は、その人と共有している「わたし」のなかの部分の死でもあるわけです。これを「部分死」と呼ぶ人もいます。わたしたちとかかわりのある人の死は、わたしたちの精神に大きな傷跡を残していくにです。例えば自分を育ててくれた親、長年連れそった配偶者、かけがえのない友人たちなどの死は、わたしたちの精神の社会的に形成された一部分が失われることにほかなりません。われわれの精神に生じた重大な傷を癒すこと、これが葬儀の役割の一つということになります。残された者の立場からいえば、他者の死を受容することといえるでしょう。 さて、死に直面したときに、それを受け入れるとは一体どのような状態をいうのでしょうか。 人間の精神のありようは人それぞれですから、一概にこれが「受容」であるなどということはできません。ここでは、自己の死であれ、かけがえのない身近な者の死であれ「死」そのものと向かい合い、その動かしがたい事実に直面し、心がさまざまに揺れ動きながらも、死を認め受け入れていく心の状態を「死の受容」としておきましょう。 |
||||||||||||||||
| 死にゆく人の死の受容 | ||||||||||||||||
| キューブラー・ロスというアメリカ合衆国の精神医学者は、回復の見込みのない病を宣告された患者は、次のような5つの心理的階段を経て死を受容していくことがあるとしています。 第一に「否認」、これは自分が死ぬなどありえないと思い込もうとする、つまりは自分が死ぬであろうことを否定することです。第二には「怒り」、なぜ自分だけがこのような目にあうのだろうかと、さまざまな怒りの感情がでてきます。第三には「取引き」、なにかと交換に自分の死を先延ばしにできないかと考えます。 第四には「抑鬱」、身体の衰弱に加え、迫り来る死を否認できないとなると患者は一時的な抑鬱状態となります。以上の階段を経過するのに十分な時間と条件に恵まれた場合に、患者は第五の「受容」へと至ることになります。ここではすべてを失わなければならないという嘆きや悲しみを乗り越え、近づきつつある自分の最期を冷静に見つめることができるようになります。 すべての死にゆく人びとがこのような心理過程を経るわけでなく、また別なプロセスを提唱する心理学者もいますが、多くの末期患者へのインタビューをもとに、彼らが死を受け入れていく過程を明らかにしたキューブラー・ロス博士の功績は非常に大きなものがあります。 しかし現在、死に至る人びとの多くは、突発的で急激な死よりも、より緩慢な死を経験します。死は、身体的な衰え=老いというプロレスの終極点として多くの人びとに用意されているからです。ここではキューブラー・ロス博士の提唱する死の心理的受容の5段階を、老いの受容への5段階と読みかえてみることにしましょう。すなわち老いを自覚しはじめたとき、老いを否認し抵抗します。そして自らが老いていくことへの怒りや、何かとの取り引き、あるいは憂鬱な気分におそわれることもあります。しかし自らの老いを十分に受け入れたうえで、残された時間を有意義に過ごそうとする人びとも少なからず存在します。その人たちにとっては、老いの終着点としての死を自覚しているという意味では、すでに死という事態を含めて受容されていると理解してもいいかもしれません。 |
||||||||||||||||
| 残された人びとの死の受容 | ||||||||||||||||
| 以上のように十分な時間と条件に恵まれた場合、死にゆく人びとはさまざまな心理状態を経過して死を受容できる場合があります。これに対して、残された遺族や周囲の人びとはどのようにかけがえのない人の死を受容するのでしょうか。 精神医学者の野田正彰氏は、大事故で肉親を失った遺族の心理的回復経過を、「ショック」「死亡という事実の否認」「怒り」「回想と抑鬱状態」「死別の受容」という5段階でとらえています。この図式は突発的な死を受け入れるための心理的プロセスについて説明したものですが、老いた肉親を看取る遺族の心理にも応用が可能なようです。先きほども述べたように、「老い」というプロセスには、必然的な終着点として「死」が約束されています。したがって肉親との長いかかわりのなかでは、はじめは相手の老いにショックを受けたり、否認したりもしますが、ついにはやがてきたるべき死をも含めて、相手の老いを受け入れていかざるをえません。この場合には、肉体的な死の訪れの前に、すでに死の受容が近親者のなかでは部分的に準備されているといえるかもしれません。 結局のところ「死にゆく人」と「残された人びと」との間には、決定的な違いがあります。「残された人びと」は、生き続けなければならないということです。他者の死をうまく受けとめることができた場合には問題がありません。だが、これがうまくいかないと、受容のために心理過程が停滞してしまい日常生活になんらかの適応障害が生じることもあります。愛する人の死は、事前にある程度予測されたものであっても、しばしば悲嘆や心の痛みをもたらします。そしてこれは病気ではなく、自然な心の現象です。残された人の悲しみや思いやり、死と向かいあいいつもそれを受容させていくための社会的、文化的仕掛けが葬送儀礼の本来の役割なのではないでしょうか。 |
||||||||||||||||
| 通過儀礼という考え方 | ||||||||||||||||
| では実際に、どのような社会的仕掛けが死の受容に役立っているかということになります。それは、文化圏ごとに多様であり、一概に論じることはできません。しかし、葬儀を通過儀礼という観点から説明し、その問題への解答の糸口を与えてくれたのはファン・ヘネップという文化人類学者です。 わたしたちは人生という長い時間をいくつかの部分に分けて考えます。その分け方はおのおのの文化や社会によって異なっています。例えばわれわれの社会では、誕生、幼児期、子ども期、青年期、成人期(独身期)、既婚期、老年期、死亡などの部分や区切りが考えられます。このようなライフステージごとに設けられた区切り(ヘネップは「敷居」と呼んでいます)を、「乗り越える」場合に行われるのが通過儀礼です。したがって通過儀礼とは、その人の社会的位置の変更をともなうものですが、そこには形式的に顕著な特徴があります。それは、ある社会的位置から別な社会的位置へと移行していく場合に、元の位置から一旦切り離され(=分離)、中間的な状態を経過し(=過渡期)、新しい位置に統合されていく(=再統合)、という形式をとるということです。こうした経過を経ることで、新しい社会成員としての自覚を当事者にもたらすと同時に、社会集団が当事者たちをあらたな社会成員として迎え入れるという役割を果たします。現代ではかなり簡略化されているものもありますが、誕生日や結婚式、成人式や還暦も本来は通過儀礼としての役割を果たしてきたと考えられます。 |
||||||||||||||||
| 通過儀礼としての葬儀 | ||||||||||||||||
| 葬儀も通過儀礼の一種として説明することができます。 人が死ぬと、死者とその遺族は「喪」という特殊な時間(服喪の期間)に入ります。それは平常の時間から分離された特殊な時間であり、かって日本では「ケガレ」の時間として考えられてきました。分離の儀礼とは、平常の時間に区切りをつけ、服喪に入るための準備の儀式です。かっては「末期の水」「魂よばい」「湯灌」などの儀式が行われてきました。しかし現在においては「お葬式」(通夜や告別式)を行うための単なる準備期間になってしまったようです。 北枕に代表されすように、服喪の期間には平常では禁止されているような行為(禁忌)をわざわざ行うことにより、死者と遺族が特別の時間にあることを強く確信し続けます。こうした特別な時間で行われる儀式を「過渡期の儀礼」と呼びます。現代の葬儀においては通夜、告別式、火葬などがこれにこれにあたるでしょう。ここでは参列者も交えて、死者を生者とは別の世界へと送るための儀式が行われます。 特別な時間や空間を経過したのち、死者は死者の世界に、生者はもとの世界に統合され、平常の時間にまいもどり、喪が明けることになります。現代の葬儀においては、統合の儀礼は必ずしもはっきりしていませんが、いわゆる「四十九日」や「一周年」などの会合がそれに相当していると考えられます。 通過儀礼としての葬儀は、遺族に特別な時間を通過させることで心理的な変容をもたらし、結果的に死を受容させていると考えることがぢきます。しかしそれは儀式や儀礼が形式的に進行するのではなく、参加する者たちによって十分な内実と精神的な緊張をともなって行われた場合においてです。かりにお金のかかった「立派な」葬儀であっても、その儀礼が心のこもらない醒めた態度で行われるものであっては、死の受容も十分には生まれてこないのではないのでしょうか。 |
||||||||||||||||
| 支え合う個人と社会 | ||||||||||||||||
| 一般に葬儀を行うためには、多くの人びとの力を借りなくてはなりません。日本の葬儀では、香典やお手伝いという形で親族や友人・知人の助力を仰ぎます。そしてその人たちとともに悲しみや精神的な緊張に満ちた時間をのりきるわけです。 細かく内用をみていくと、葬送儀礼に は共同作業が多く含まれています。一人でたやすくできることを、わざわざ複数の人間が儀礼的な共同行為として行う場面があります。たとへば、火葬後の拾骨の儀式で、必ず二人で箸わたしをする場面を思い出していただければわかりやすいでしょう。遺体の処置という、遺族にとってもっとも過酷な作業を、複数の人間がともにわかちあうという象徴的な儀礼だと考えることができます。 このような葬儀には、社会関係を感じさせる「仕掛け」が数多く用意されています。これらが「しきたり」や「しがらみ」として、長いこと人びとを縛りつけてきた側面を見逃すことはできません。 しかし、人の死という現実に直面したときに、葬儀の社会的な部分がすべて排除され、死を受けとめるのは個人でしかないという状況になったときには、「死」は耐え難いほどに重いものとして、われわれにのしかかってくるということもあるのではないでしょうか。 このように考えてくると、葬儀とは、身近な他者の死という最も過酷で厳粛な場面に直面した人びとに対して、悲しみを和らげるための共同行為として考えることができるのではないでしょうか。 |
||||||||||||||||
| 葬送の変化・TOP | ||||||||||||||||
|
安心料金・安心価格の葬儀社・セレモニーユニオン
|
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||