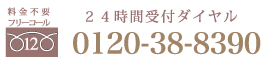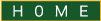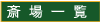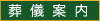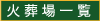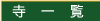| ●法事の心得
法事は仏法の行事を意味します。仏事、追善(追薦・追福)供養、年回(年忌)などともいいす。
月一度の命日にお寺さん参っていただく月忌(がっき)、お盆やお彼岸など年中行事になってい
るもの、七回忌・十三回忌ように何年かに一度の年回法要、五十回忌・百回忌などかなり大がか
りなものとその規模もさまざまです。
親類や友人・知人など故人と縁のあった人が集まって法事は行われます。このとき、法事を営む
側も招かれる側も、何回忌だから集まるという形式的な考えだけでは、なんのための法事かわか
りません。法事はあくまで故人への感謝の気持ちから行われるべきものです。今のわたしたちが
あるのは、父母や祖父母、さらにその父母といったご先祖さまのおかげです。一緒に生活してい
るときに感謝の心を示すのはもちろん、亡くなってからも感謝の気持ちを持ち続ける、そのため
の法事です。
むかしは、法事のために家を直したり、お仏壇を買い替えたりもしたようです。いま、そこまで
するのは無理ですし、各家の事情に合わせ、気持ちのこもった法事が営めればそれでいのです。
法事という仏法の行事を通して、仏さまやご先祖さま、亡き父母を敬う気持ちを確認し、これ
からもおつかえしていくことを誓うのが何よりも大切です。
●法事の準備
法事を準備しているときから、すでに法事は始まっているという心構えが必要です。心をこめて
法事を行いたいと思えば、自然と準備もきちんとしてくるはずです。しかし、はじめて法事を営
む場合、どのように準備すればいいのか、とまどってしまうものです。法事の準備としてやらな
ければならないことは、次の六つです。
1)日時を決める
最初に、法事の日時を決めます。営む側の都合だけでなく、お寺さんや来ていただく方にも予定
がありますから、なるべく早く決めることです。忌日からずらすことはしかたありませんが、遅
らせよりは、早い日を選びましょう。また真夏や真冬でお年寄りの健康が気づかわれるときは、
気候のいいときを選んでもかまいません。
2)法事の規模を決める
法事の規模といっても決めなければならないことはたくさんありますから、各家の事情に合わせ
て決めます。
●お客さまを何人ぐらいお招きするか
●場所はどこにするか(自宅・お寺・会館・霊園などの礼拝堂)
●引き出物は(記念品・お土産)はどの程度にするか
●お寺さんへのお布施は(自宅や墓地に出向いてもらう場合、送迎してもしなくても
「御車代」を包みます。供応しない場合、「御膳料」をつつみます。
●仏さまへのお供えは
3)案内状を出す
お招きする人が決まったら、出来るだけ早く案内状を出します。特に書式が決まっているわけで
はありません。心をこめて書けばよいのです。
4)役割を決める
法事の前に、次の三つの係りを決めておくようにします。
●法役(線香やロウソクを替えたり、焼香の準備など、お仏壇のお世話をする係り)
●接待係
●台所の責任者
5)会場づくりをする(自宅の場合)
●移動可能なお仏壇の場合、最も奥まった参詣者の正面に安置します。
●作りつけのお仏壇の場合、わきにお供え物の祭壇を設けます。
6)引き出物を用意する
●どの家庭でも使う物がよいでしょう。
法事の進行
読経(法事の読経は30〜一時間禁煙をやめ私語をひかえます。読経中に参拝者全員が
焼香します)
法話(10分〜20分
お斎=会食(お礼挨拶をのべます。このとき引き出物を出してもかまいません)
|